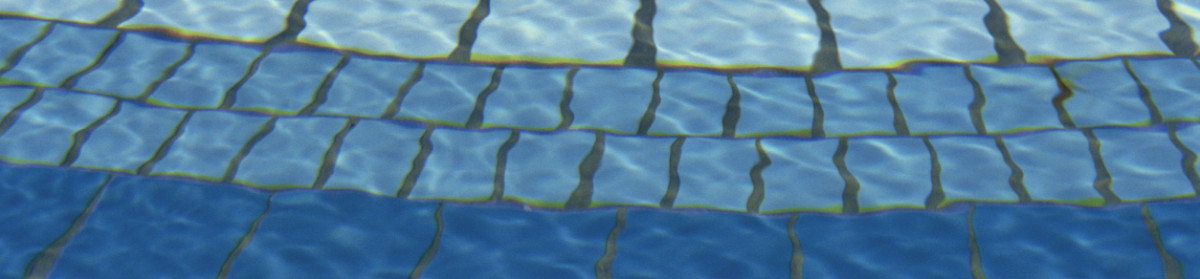こんにちは。
心理相談室 LAUNDRY カウンセラーの村本大志です。
もうすぐ春が来る・・のでしょうか。
今日は暖かく過ごしやすいですね。
映画『グッド・ウイル・ハンティング』は、 春 を感じる作品です。
観たことがある方もとても多いと思います。
この映画の製作当時から考えると、次作のバットマンをベン・アフレックが演るというのもなんかすごいキャスティングですが90年代から活躍しているのでアメリカ人にとっては自然なのかもしれないですね。
その若きベン・アフレックとマット・デイモンの幼馴染二人で脚本を書いたものが、この作品『 グッド・ウイル・ハンティング 』です。
ベン・アフレックも主人公の地元の不良友だちとして味のある役で出演しています。
幼少期の激しいトラウマから心を閉ざしている不良めいた数学の天才少年が(設定年齢21歳)妻を失くした失意の中年心理学者と心を通わせ、新しい人生の一歩を踏み出す・・。
と書いてしまうとシンプルですが、この映画も語り尽くせない魅力がいくつもあります。
中でもロビン・ウイリアムスの奥深い演技にはやはり心を奪われます。
目がいいんですよね。
思慮深く
悲しみをたたえ
慈悲深い
そんな瞳です。
若きマット・デイモンの真っすぐな芝居を横綱相撲でがっちり受け止めているんです。
あんな風に受けられたら若い役者は嬉しいだろうなぁ・・(しかも今回は自分で書いた脚本ですから)
演技とは、かくも人間力が反映されてしまうとすると、実に奥深いものです。
ガス・ウ”ァン・サントは音楽の使い方がとてもうまい監督です。
ある意味、この作品は正当派な映画なのですが、映画音楽がインディーズ映画的な匂いを醸し出すものですからハリウッド・メジャー的な感じがあまりしない。
どこかサブカルチャーな雰囲気を残してくれていて嬉しい。
キャストのバランス感も見事です。
ヒロインのミニー・ドライウ”ァーも2000年代のハリウッド映画のヒロインとはひと味違うクセのある顔立ちです。
彼女の演技も愛する男の心をなんとか開こうとするところなんか、とてもぐっとくるものがあります。
カウンセリング・シーンは、リアリティより物語を進行させることを選んだのでしょうが、ロビン・ウイリアムス演じる心理学者は、頑なに<人生の選択をするのは本人であり、私は彼が話すのを待つだけだ・・>との姿勢を崩さないあたりは本道から外していませんし、それがそのままこの映画の主旋律でもあります。
アメリカ映画の中に心理学者やカウンセラーが登場すると、ほぼ彼らも問題を抱えていたり影を引きずっていることが多いです。その辺りは映画的な仕掛けの意味合いもあるでしょうけど、彼らが決して聖人ではなく市井の人々であることを示唆しています。
映画『グッド・ウイル・ハンティング』のもつ魅力的なシーンはいくつもありますが、やはり主人公と心理学者の心が本当に触れあう瞬間の素晴らしさに他ならないでしょう。
そのシーンでの二人の斜に構えない演技は、まっすぐに人の心を打つものがあります。
< 演ずる技術 >が同時に備わったこの映画のピークです。
多分、90年代の終わりのアメリカ映画って、こういうものがこういう風に描かれる最後かも知れません。
2000年代に入ると、もっと設定が複雑でダークで、デジタルを絡めた物語が多くなっていきます。
携帯も登場せず(雨の中、公衆電話彼女に電話する!)Macらしきものはありますが、あくまで背景の小道具の範囲内で、使用すらされないのです。
あくまで登場人物たちはアナログに関わり合い、不器用にもがきます。
デジタルの普及は我々の生活を便利にしてくれました。
映画もはるかにデジタル技術力があがり表現の幅も広がりました。
それでも、心を本当に打つものは生身の俳優が(人間が)
登場人物になりきった瞬間なのだとこの映画を見直してみて改めて思った次第です。
カメラワークはあくまでシンプルで、ナチュラル。物語を進行するためだけに尽力を捧げています。
とても美しい撮影です。
ちなみに、この映画の原題は『GOOD WILL HUNTING』で邦題と同じです。
主人公の名前も WILL HUNTING というのですが、直訳したり意訳してみたりすると
なかなか含蓄がありますよね。
英語って、こういう韻を踏むと詩的です。